泡の原因として汚水に洗剤が多く含まれての泡の発生と、微生物の活性による泡の発生などが考えられます。浄化槽の機能が正常に戻れば、泡も消えますが、急ぎで泡を消すためのアワカットOX(固形消泡剤)などが市販されています。
また、当社管理のお客様へは無料対応しています。
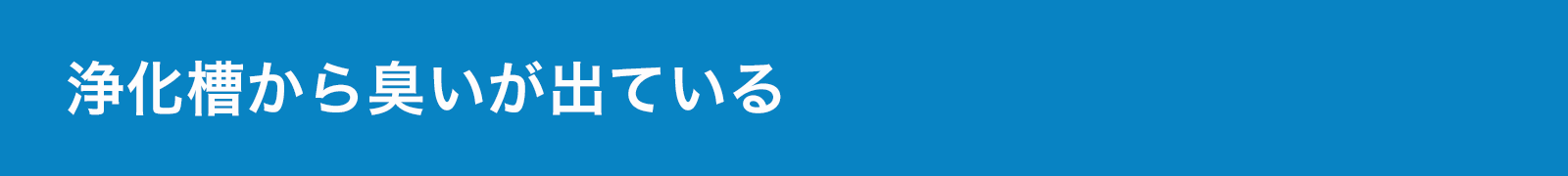
 臭いの原因は複数ありますが、浄化槽に空気を送るブロアーと言う装置が不良か止まっている事が原因の場合があります。
臭いの原因は複数ありますが、浄化槽に空気を送るブロアーと言う装置が不良か止まっている事が原因の場合があります。
もし、止まっていると、浄化槽内で微生物が活動出来ないで、浄化されず臭いを出していることが考えられます。また、ブロアーが正常に稼働している場合は、家庭から流入する汚水に原因が有る場合や、浄化槽の他の箇所の不良もあります。ブロアーの確認は動いているかですので、確認をしてみて下さい。それでも臭うが止まらないは……

 トイレの詰まりの原因として、トイレから浄化槽までの間で、配管内やトイレそのものに詰まりがある場合と、浄化槽内部などの詰まりがあります。
トイレの詰まりの原因として、トイレから浄化槽までの間で、配管内やトイレそのものに詰まりがある場合と、浄化槽内部などの詰まりがあります。
簡単な詰まりでしたら、ラバーカップなどで対応可能です。トイレから離れた配管内部ですと、なかなか簡単な機材では詰まりが解決できません。そのような場合は高圧洗浄機で配管内部の洗浄を行います。

 浄化槽は汚水を放流出来る水にするための槽ですが、また虫にとっても住みやすい場所と言えます。
浄化槽は汚水を放流出来る水にするための槽ですが、また虫にとっても住みやすい場所と言えます。
全く虫が居ない環境では無いため、少しの虫の発生はありますが、異常発生では、浄化槽の微生物に影響が出ないような殺虫剤の使用が必要です。
闇雲に殺虫剤を散布すると、微生物に影響を与え、臭いが発生することがあります。
どんな薬剤が良いかなど、多々有りますのでご相談下さい。
浄化槽は微生物が汚水の有機物をた食べて分解し、沈殿物を作ります。
浄化槽内に沈殿物(汚泥)が溜まるため、最低でも1年に1回の汚泥引き抜きが定められています。
では、汚泥引き抜きを行わないとどうなるのでしょうか?
微生物の活動する空間が狭くなり、放流するが放流可能な水質に維持出来なくなります。
また、汚泥が沢山溜まると、引き抜き量も多く、固着して引き抜き自体が困難になったり、浄化槽が壊れることや、いろいろな費用が発生する可能性があります。
定期的な汚泥の引き抜きは重要です。
浄化槽をお使いの場合、下記3つで費用が掛かります。
お客様に代わって、浄化槽を適正にするために、定期的にお伺いして、浄化槽を点検し、不具合の改善を行います。
対応先:富士コントロールや、他の浄化槽管理会社
浄化槽から汚泥を引き抜きます。
対応先:地域指定の清掃業者
国が定めた機関がお客様の浄化槽が適正か検査を行います。
対応先:各県の浄化槽協会
3)の機関の検査から通知が来た場合、検査が必要になります。
1)での保守点検での検査は、維持管理するための検査で、3)の検査は国が進める浄化槽が適正に管理されているかを調べる検査となります。
 浄化槽は水中の微生物の働きを利用して汚水(し尿、雑排水)を浄化するものです。微生物が働きやすい環境を維持出来ないといろいろと問題が発生します。定期的な管理は必須です。
浄化槽は水中の微生物の働きを利用して汚水(し尿、雑排水)を浄化するものです。微生物が働きやすい環境を維持出来ないといろいろと問題が発生します。定期的な管理は必須です。
浄化槽が正常に機能していないと、河川を汚すことになります。
そのため、浄化槽法と言う法律で管理方法が決められています。
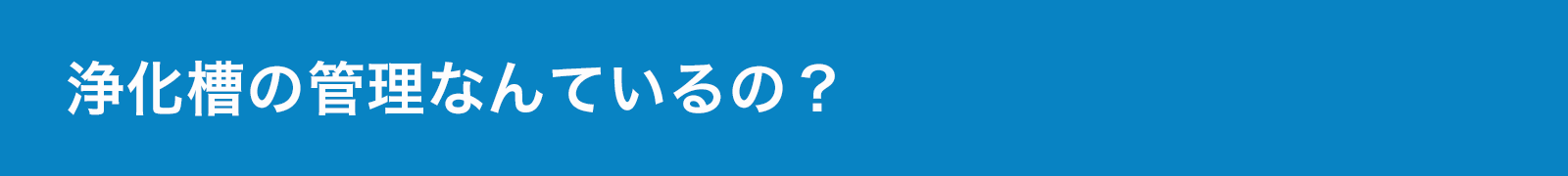 排水を敷地内から放流する場合、法律で定められた方法が決められています。
排水を敷地内から放流する場合、法律で定められた方法が決められています。
浄化槽法(じょうかそうほう、昭和58年5月18日法律第43号)は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造についての規制、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度の整備、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することが目的である。
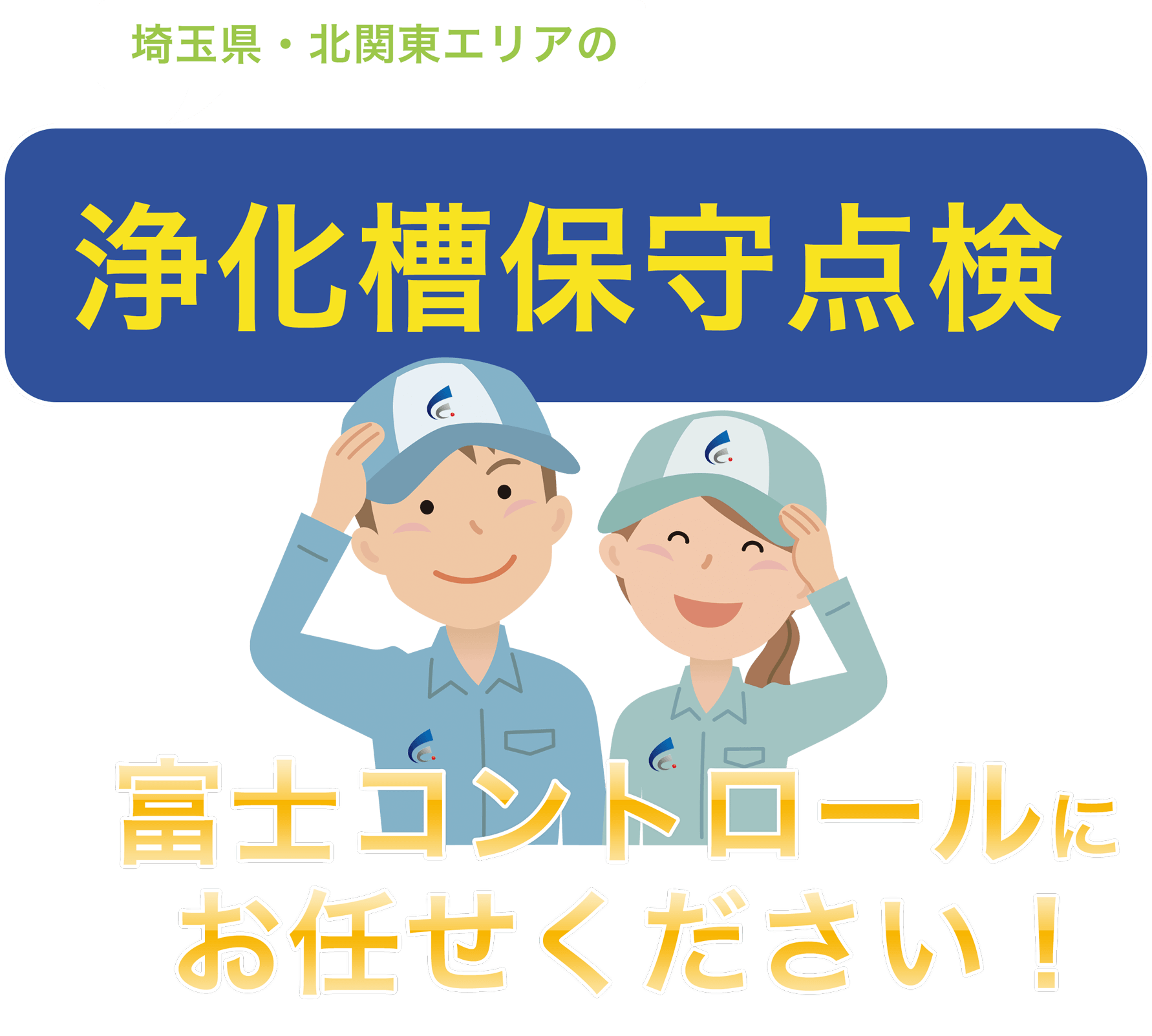

当社は事前アポイントの上、在宅点検をおすすめしています。
長年培ったノウハウを是非一度見て下さい。
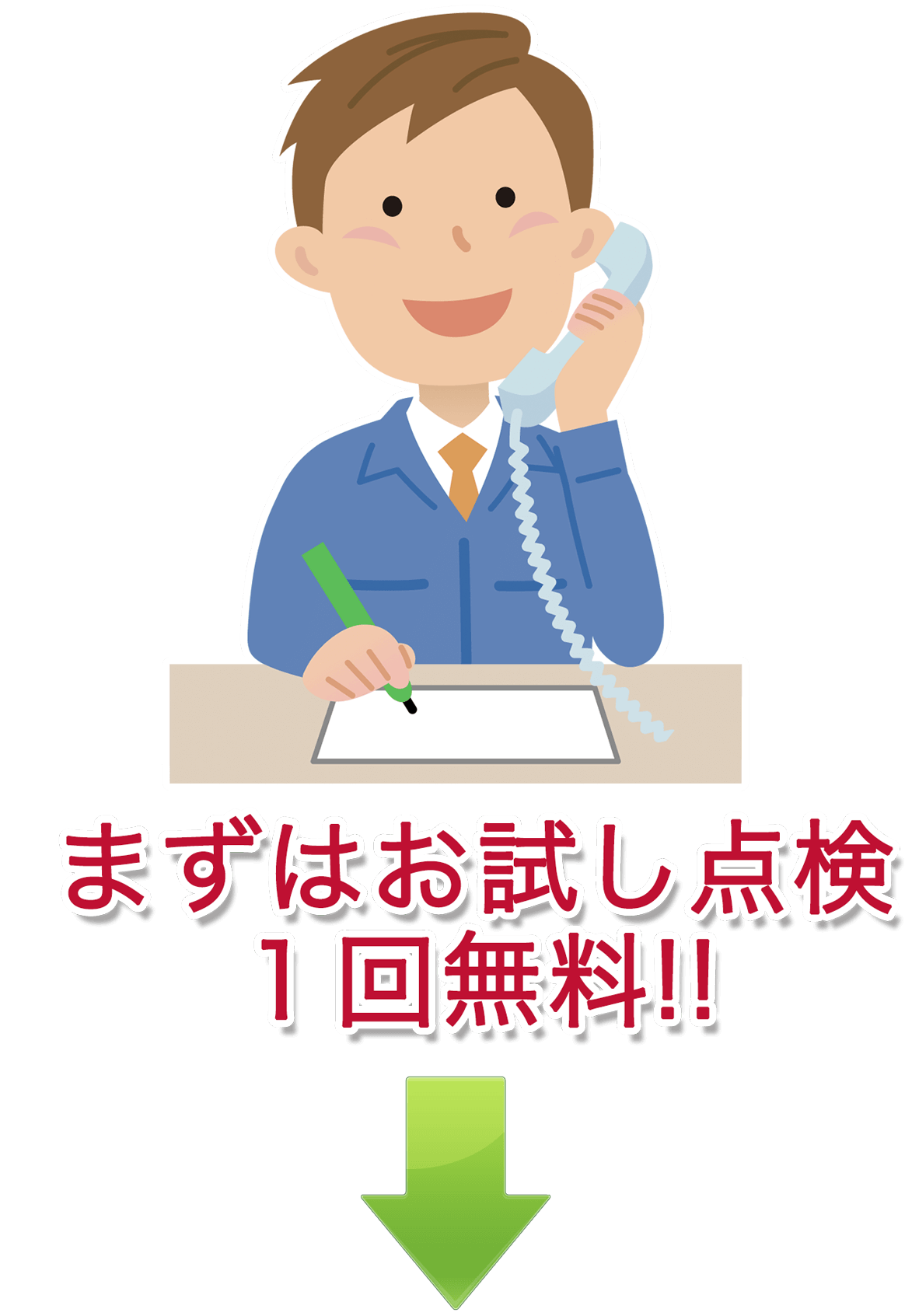
浄化槽の機能を維持するために、機器類の調整や消毒薬の補充等を4ヶ月に1回以上実施しなくてはなりません。(処理方式や処理対象人数によって回数は異なります)保守点検は浄化槽管理士のいる専門の登録業者が行います。
浄化槽には、少しずつ水に溶けない固形物や汚泥が溜まっていきます。そのままにしておくと、臭いや水質悪化の原因になります。清掃では、汚泥の引き抜き等を年に1回以上行わなければなりません。清掃は市町村の許可業者が行います。
浄化槽の機能がきちんと確保されているか確認するのが法定検査です。保守点検・清掃とは別に法定検査(11条検査)を年に1回必ず受けなければ なりません。浄化槽を新たに設置し、使用開始後3ヶ月~8ヶ月以内に 実施する法定検査(7条検査)もあります。
